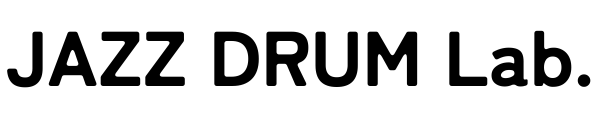今回は2024年11月12日「99歳」で遂に旅立った伝説的なジャズドラマー「Roy Haynes / ロイ・ヘインズ」について触れてみたいと思います。
生い立ち

Roy Owen Haynes / ロイ・オーウェン・ヘインズは、1925年3月13日にマサチューセッツ州ロクスベリー(ボストン)で生まれました。
幼い頃から家のものを叩いては壊してしまったそう。それを見かねた父親からドラムのレッスンを地元のドラマーであるHerbert Wrightに勧められます。
音楽一家に育ち、若い頃からジャズに触れていたロイは、チック・ウェッブやシド・カトレットなどのジャズドラマーの偉人を紹介され、更にドラミングへの情熱をかき立てました。
高校時代からサビー・ルイス楽団、フランキー・ニュートンのバンドで活動。
19歳からニューヨークへ拠点を移し、本格的にプロとして活動開始。そのキャリアは70年以上にわたっています。
孫には同じく現代を代表するドラマーのMarcus Gilmore / マーカス・ギルモアがいます。
年代別活躍
1940年代初頭
地元のバンドで演奏技術を磨いた後に、ニューヨークへ進出。サックス奏者ルイス・ラッセルとのプロデビューを果たします。
その頃キング・オリバー、ルイ・アームストロングとも共演。
1949年
チャーリー・パーカーのバンドに加入し、キャリアにおける転機に。
パーカー、ディジー・ガレスピー、その他のビバップの革新者たちと共演する中で、ロイは独自のスタイルを発展させていきます。
1950〜1960年代
セロニアス・モンク、ジョン・コルトレーン、マイルス・デイヴィスなど、ジャズジャイアンツとの共演を重ねます。
後にロイは自らのグループを率い始め、作曲家やバンドリーダーとしてのスキルを披露しました。
チック・コリア、パット・メセニー、ゲイリー・バートンなどのミュージシャンが彼の下で育ち、若手の才能の温床となりました。
1970〜1980年代
フュージョンやアヴァンギャルド・ジャズを受け入れ、新しいサウンドやテクスチャーの実験を行いながらも、ロイの特徴的なグルーヴと即興を保ち続けました。
絶え間なくジャズシーンで活発に活動し、ジャンルへの貢献に対する批評家からの称賛や数々の賞を受賞します。
現在
2024年11月12日に死去。99歳没。
亡くなる寸前まで世界中で演奏し、彼の遺産はジャズのアイコンとして確固たるものとなっています。
革新的な演奏スタイルと不屈の精神は、楽器を超えジャンルを超えて音楽家たちにとっての指標となっています。
年代別の共演者と代表的な音源

前期キャリア(1940年代〜1950年代)
- チャーリー・パーカー : Charlie Parker with Strings (1950) South of the Border (1952)
※トラックにより他ドラマー参加 - ディジー・ガレスピー : The Complete Live at Birdland(1951,53)Track 1~4
- マイルス・デイビス : Miles Davis And Horns(1951,53)
- サラ・ヴォーン : SARAH VAUGHAN AND HER TRIO At Mister Kelly’s(1957)
- セロニアス・モンク : Thelonious In Action(1958) Misterioso(1958)
- ジョン・コルトレーン :Impressions(1963) Track 4,5 Dear Old Stockholm(1965)
中期キャリア(1960年代〜1970年代)
- スタン・ゲッツ :The Stan Getz Quartet, at the London (1966)
- ゲイリー・バートン : Duster (1967)
- チック・コリア : Now He Sings, Now He Sobs (1968)
後期キャリア(1980年代〜現在)
- パット・メセニー : Question and Answer (1990)
- ゲイリー・バートン : Like Minds(1998)
リーダー
- We Three (1958)
- Out of the afternoon(1962)
- People(1964)
- Senyah(1973)
- Live at the Riverbop(1979)
- Truth or False(1986)
- The Roy Haynes Trio Featuring Danilo Perez And John Patitucci(1999)
演奏スタイル
ロイの演奏スタイルは確かなテクニックがありつつ、伝統的なジャズの語彙を革新的なリズムのコンセプトと自然に融合し、伝統と先見性の両方を備えたサウンドを創造しています。
特徴の一つとしてハイハットの自由度が挙げられます。
一部界隈では有名な話ですが、駆け出しの頃はお金がなく、スネア ・ライドシンバル・ハイハットしか買えなかったそうです。
それによりハイハットをバスドラム的に使ったり、スネアのコンピングのように使ったりと可能性を模索したのだとか。
同じくハイハットの革新的な使い方をしたトニー・ウィリアムスにも影響を与えました。
特に自由度の高いフレッシュな演奏が聴けるのはこのアルバムではないでしょうか。
Now He Sings Now He Sobs(1968)
単に複雑なフレーズをしているのではなく、全てメロディのように繋がっているのが驚異的です。
以前に見かけたインタビューでは「演奏した内容は全て覚えている」と言っていました。
当時は本当に?と思いましたが、ロイの演奏を知れば知るほど、それほど全ての音に意思を行き巡らせているのが分かります。
またこのアルバムで聴かれる特徴的なライドシンバルサウンドと、推進力のあるグルーヴはモダンジャズドラマーのアイコンになりました。
ベルが無い「フラットライド」はサスティンが短く、クリアな粒立ちが特徴的で、今でも色褪せない現代的なサウンドを放っています。
スネアドラムも同様に印象的で、迅速なロール、鮮明なアクセント、自由な手順、複雑なポリリズムにより、ドラムにメロディックさを与えています。
ロイの即興スキル、マインドは他に類を見ませんが、唯一受け継いだとみなされるのは孫である「マーカス・ギルモア」ではないでしょうか。
しばしばロイとマーカスは異なると言われますが、マーカスの演奏からはロイが自分の言葉を作ってきたのと同じ様に、自分独自の言葉を持っている様に思われます。
そして何よりもロイが驚異的なのはいくつになっても「フレッシュ!」であることです。
90歳を超える今でも、演奏からはエネルギッシュさ、創造性、そして純粋な喜びが感じられます。
ドラマーの宿命ですが、加齢と共に速いシングルストロークや、複雑な足の組み合わせ等は難くなってきます(奏法にもよりますが)。
特に筋肉量が比較的多い黒人ドラマーに見られます。
しかしロイは当時行った事を焼き回しするのではなく、音は必要な時に演奏し、その時に出来る事を等身大でやっているから色褪せないのかなと感じます。
ビッグバンドをリードしたり、ファンキーなグルーヴを刻んだり、最先端のフリージャズまで、その音楽”らしく”演奏するのではなく、常に自分のサウンドを使ってアプローチしているのが伺えます。
参加とリーダーシップ
1. チャーリー・パーカー
1940年代後半のチャーリー・パーカーのバンドでのロイの在籍期間は、キャリアにおける形成期となりました。クインテットの一員として、ロイはビバップにおけるドラマーの役割を再定義し、新しいリズムアプローチを開拓し、技術的な熟練度の高い基準を設定しました。
2. 1960年代のリーダーシップ
1960年代にロイはバンドリーダーとしての地位を確立し始め、自身のグループを結成し、プレスティージ・レコード向けに一連の評価の高いアルバムを録音しました。
チック・コリアやゲイリー・バートンなどの新進気鋭のスターをフィーチャーした彼のバンドは、次世代のジャズミュージシャンを育てる才能を示す場となりました。
3. フュージョンの探求
1970年代から1980年代にかけて、ロイはフュージョンムーブメントを受け入れ、ロック、ファンク、アヴァンギャルド・ジャズの要素を自身の音楽に取り入れました。
チック・コリア・エレクトリック・バンドやパット・メセニー・グループの一員として、ロイはジャズの枠組みを押し広げ、自身の特徴的なグルーヴと即興の才能を保ちながら、新しいサウンドやテクスチャーの実験を行います。
4. 持続的なリーダーシップ
一般的に「高齢」と呼ばれる年齢であるにもかかわらず、ロイはジャズコミュニティで活発で影響力のある人物として活動を続けていました。
自らのグループを率い、リーダーとして60枚以上のアルバムを録音し、さらに数百枚のサイドマンとしてのアルバムも残しています。
キャリアを通じて、ロイは数え切れないほどのミュージシャンにメンターとしてまたコラボレーターとして奉仕し、次世代のジャズアーティストに自身の知識と経験を伝えてきました。
ジャズの驚異的な伝説としてその遺産は将来の世代に受け継がれることでしょう。
5. 数々の受賞
ロイのジャズへの貢献は見過ごされることはありませんでした。
ダウンビートの殿堂入りを果たし、グラミー生涯功労賞を受賞し、その他数々の賞に輝いています。
これらの賞はロイのジャズ界への持続的な影響力と、ジャズ史上最も偉大なドラマーの一人であることを証明しています。
まとめ
スウィング時代の初期からビバップにおける画期的な活動、さらに最先端のジャズに至るまで、ロイはジャズ界の最前線に立ち、リズムと即興の限界を常に拡張し続けてきました。
単なるジャズドラマーに留まらず、ドラムキットの枠を超えて伝説となったミュージシャンです。
自身がロイを見たのは学生の時でした。当時86歳?ぐらいの頃。
赤ワインを片手にドラムセットに向かう姿は大御所の雰囲気ありまくり。
当時はジャズドラムは音が小さくてスマートなもの、と偏った考えがあったので、ロイの音の大きさとフレーズの大胆さにビックリしたのを覚えています。
初めは正直あまり理解できていなかったのですが、あの年齢で驚異的なことをしていると気付いたのは数年経ってから…
今でも新しい気づきを与えてくれるスーパージャズドラマーです。
ご冥福をお祈りいたします。